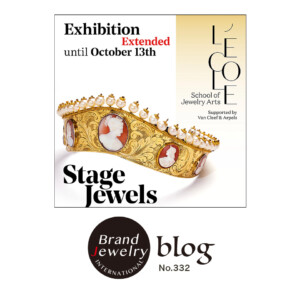NO.392 世界各地で古代から習慣化されていた口元の装い。過去と現代の事情に迫る!
口元からちらりとのぞく輝く歯。現代では白い歯が美しいとされていますが、日本では、明治初期まで既婚女性の間では歯を黒く染める「お歯黒」が広まりました。
お歯黒の起源ははっきりしませんが、南はインドネシア、東はソロモン・マリアナ諸島、北は日本、西は中国南部とインド南部にわたって形成されていたことがわかっています。
日本におけるお歯黒の歴史は古く、3世紀末に書かれた『三国志』魏志倭人伝の冒頭に「歯黒国アリ」という記載もあり、当時からすでに定着していたと推測されます。お歯黒は、女性だけがしていたものと思われがちですが、かつては男性にもその風習がありました。平安時代初期、貴族の女性は裳着(もぎ)、貴族の男性は元服と呼ばれる成人の儀式としてお歯黒をしていたそうで、平安後期には公家や武家の男性も行っていたようです。
江戸時代に入ると男性のお歯黒文化は廃れ、一方で庶民の既婚女性の習慣となっていきます。当時の浮世絵にも女性がお歯黒をしている姿が描かれています。お歯黒は、口紅やおしろい、まゆ墨などとともに、女性の化粧の道具の一つでした。
またお歯黒に使うお歯黒水には、収れん作用のあるタンニンが含まれているため、歯や歯ぐきを保護する役割があり、虫歯予防としても広く認知されていたとか。
黒が選ばれた理由としては諸説ありますが、何色にも染まらない=貞節の証という説や、黒いつやのある歯は美しいという価値観がありました。
北海道のアイヌ民族の女性は、シヌイェと呼ばれる口の周りに入れ墨を入れる習慣がありました。これも貞節の証を意味していたという説があります。同様にニュージーランドのマオリ族にも、口元から顎にかけて入れ墨を入れる風習があります。2020〜2023年ニュージーランドの外相を務めたマオリ族のナナイア・マフータ氏の口元にも入れ墨があり、顔にタトゥーをした最初の女性国会議員と話題になりました。
日本ではお歯黒、シヌイェは、明治政府の近代化政策により禁止され、次第に衰退、今では見られなくなりました。そして現代、口元の装いといえば、歯の上に装着するジュエリー、grill(グリル)がアーティストを中心に流行しています。アメリカではヒップホップのスターたちがこぞって着用しています。日本でも、ラッパーの間で人気のアイテムのひとつです。素材はゴールドや宝石を使ったゴージャスなものがあり、お歯黒の黒い艶とはまた違ったインパクトがあります。
グリルは最近のジュエリーなのかと思っていたら、実は2500年以上の歴史を持っていたことがわかってきました。『ナショナル・ジオグラフィック』のサイトによると、メキシコ南東のチアパス州で発見された頭蓋骨の歯には、派手な装飾物が埋め込まれていました。グリーンや赤、ターコイズブルーの石がきれいに施され、当時からすでに歯の構造について高度な知識や技術を持っていたこともわかっています。
メキシコ国立人類学歴史学研究所(INAH)が所蔵している歯の調査を行ったところ、北アメリカ南部の古代人は歯に刻み目や溝を施したり、宝石などの装飾物を埋め込むために歯医者に通っていたことがわかりました。それも男性が、社会の階級を表すのではなくファッションとして行っていたと分析されています。
時代や環境によって変化していく口元の装い。もしかしたら、またお歯黒の時代がやってくるかもしれません。
画像出典:ja.wikipedia.org

曲線が美しい柔らかなハートシェイプのペンダントトップ。どんな服にも合いつつ、平凡ではないジュエリー。シルバーxプラチナの耐久性のある素材。メレダイヤモンドが煌めきます。
オンラインショップはこちら。

バロックパールが蜂が止まっている様子を描いた大人可愛いネックレス。上品だけどポップな雰囲気もあるデザイン。蜂は幸運をもたらし、強運になる、災害を防ぐなど意味し、日本でも海外でも人気のモチーフです。スペイン製
オンラインショップはこちら。
メンバーの方には一足先にお得情報をお知らせします。会員登録はこちらから
https://brandjewelry.shop/usces-member/?usces_page=newmember